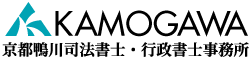親が認知症になったら相続はどうなる?事前にすべき対策5選
2024/01/10
近年、高齢者の認知症患者数が増加しています。認知症になると法律行為ができなくなるため、相続に関する手続きは困難になります。両親に認知症の症状が現われる前に、早めに相続対策をしておくことが大切です。
今回は親が認知症になった場合の相続対策について解説します。今のうちにやっておくべき対策についても詳しく紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.親が認知症になった場合の相続対策
もしも既に親が認知症になっている場合、相続対策はどうなるのでしょうか。
1-1.親が認知症になったら相続対策はできない
認知症の診断を受けると、法律的には判断能力がないとみなされ、法的な行為は無効となります。そのため、相続対策として贈与や遺言の作成、不動産の売買などを行ったとしても、認知症と判断された後であればすべて無効とされてしまうのです。
日本では、高齢化が進むにつれて認知症の患者数も増加しており、2025年には約700万人、すなわち高齢者のうち5人に1人が認知症になると見込まれています。また、認知症の一歩手前とされる軽度認知障害(MCI)の発生率も15~25%と推定されています。これらの数字から、認知症は私たちにとって身近な問題であることがわかります。
1-2.認知症発症後利用できるのは法定後見制度のみ
認知症により判断力が失われた際、法定後見制度を利用することで、資産管理や契約などを代理で行うことができます。しかし、後見人は家庭裁判所が選任するため、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く、親族の思い通りにはできない可能性が高いです。
この制度は、主に本人の財産を保護することが目的であり、積極的な資産運用は許可されていません。不動産売却などの大きな取引は、本人に明確な利益がある場合のみ可能です。単純な管理の煩わしさなどの理由では認められません。
このように、法定後見制度は、相続人の利益に焦点を当てた相続対策には用いることができないのです。これには、遺産分割や節税対策など、相続に関連するトラブル防止の措置が含まれます。結局のところ、法定後見制度を使用しても相続対策は行えないのが現状です。
2.親が認知症になるとできなくなること
親が認知症になった場合、相続対策として以下のような法律行為ができなくなります。
- 預金口座の解約や振込み、引き出し
- 不動産の売却
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 生命保険の加入、請求
- 遺産分割協議への参加
- (株主の場合)議決権の行使
このように、親が認知症になってから相続対策をするには多くの弊害が生じてしまいます。
「うちの親はまだ大丈夫だろう」と対策を先延ばしにしていると、いつのまにか症状が進行していることもあるため、判断能力がはっきりしているうちに相続対策をすることが大切です。
3.親が認知症になる前にやるべき対策5選
認知症が進むと、判断力が衰え、相続対策ができなくなります。そのため、認知症になる前、または症状が深刻化する以前に、適切な相続準備を行いましょう。
親が認知症になる前にやっておくべき対策は以下の5つです。
3-1.対策①遺言書の作成
遺言とは、個人が自己の財産を死後誰に何を継承させるかについての最終的な意向を示すものです。認知症になっていたとしても軽度でまだ意思判断能力がある場合、遺言書を作成することが可能です。遺産の分配を事前に定めることで、相続に関する争いを防ぐことができます。遺言者の意思決定能力が後に問題となるリスクを減らすために、自筆で書く遺言よりも公証人が介在する公正証書遺言の作成がおすすめです。遺言書は判断能力がなくなってからでは無効とされてしまうので、早めに作成しておいてもらいましょう。
3-2.対策②生前贈与
生きているうちに子どもや孫へ財産を譲る生前贈与も有効な対策です。認知症発症前に行っていれば、その後認知症によって判断力が失われたとしても、贈与を受けた子どもはその財産を自由に扱えるようになります。
ただし、年間110万円を超える生前贈与は贈与税が課されることがありますので注意が必要です。贈与税には多くの控除や特例があるため、これらを活用するためにも、生前贈与を計画する際には贈与税のシミュレーションを行い、適切な控除や特例を利用することが重要です。
3-3.対策③委任契約
委任契約は、親族や専門家などの第三者に財産管理等を任せるための契約です。この財産管理には、銀行取引のほか、債務や税金の支払い、保険、さらには売買や賃貸契約などが含まれます。あとに説明する任意後見制度と違い、契約締結後からすぐ効力を発揮するため、判断能力がはっきりしている時点からサポートを受けることができます。また、原則後見監督人は不要です。
しかし、認知症により判断力が衰えた場合、委任契約を結ぶことはできません。もし契約が成立しても、本人が委任する内容を理解していなければその契約は無効となり、代理として行われた行為も無効になります。
なお、認知症対策としては、任意後見制度とセットで利用することが一般的です。
3-4.対策④任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が衰えた時に備え、事前に自身の財産の管理や処分を委ねたい人と契約を結ぶものです。健康で意思決定が可能なうちに契約しておくことで、認知症になった場合の財産管理を自らが選出した後見人に任せることができます。
委任契約と似ていますが、この契約は公正証書で作成する必要がある点、後見監督人の介入が必須である点などの違いがあります。また、任意後見制度は判断能力が低下したときに効力を発揮するため、認知症対策としてより有効です。
任意後見制度には以下の3つのタイプがあります。
- 将来型:将来的に判断能力が低下した際に発動する
- 移行型:事前に「財産管理委任契約」を結び、判断能力が低下した場合に移行
- 即効型:契約が成立した直後から効力が生じる
前述した委任契約の場合、本人の意思決定能力が低下すると本人の意思通りに財産管理をすることが困難となります。そのため、意思決定能力がなくなる前から任意後見制度を契約しておくか、任意後見制度へ移行させるのがよいでしょう。
3-5.対策⑤家族信託
家族信託は、成年後見制度に比べてより柔軟で自由な財産管理・運用が可能です。ただし、家族信託を結ぶ際には、委託する親が認知症になる前に行う必要があります。
家族信託とは、自分の財産を信託し、家族メンバーがこれを管理、運用する契約です。この契約では、「委託者」が財産を信託し、「受託者」が管理・運用する。さらに、「受益者」が運用利益を受け取るという特徴があります。受益者は委託者や受託者と同一であっても構いませんし、委託者が亡くなった後に受託者が受益者となるよう設定することも可能です。
家族信託では、財産処分の権限を受託者に渡すことで、委託者が意思決定能力を失っても、財産の管理・運用を継続できます。また、契約により、委託者の死後の財産権の引き継ぎ先を定められ、これは遺言に相当する効果があります。
家族信託契約を締結する際は、契約書を作成し公証役場で公正証書とすることが一般的です。信託契約は書面がなくても有効ですが、紛争を避けるために契約書を作成し、これを公正証書にすることを推奨します。これにより、紛失、盗難、改ざんなどのリスクを防げます。
4.まとめ
認知症発症後の相続対策は困難であり、スムーズな相続ができなくなります。重要なのは、親の判断力がはっきりしているうちに早めの対策をすることです。認知症になる前であれば、相続対策の選択肢が複数あるため、自分の家族に合った方法で対策ができます。「うちの親はまだ大丈夫」と油断せず、今のうちに親子で相続について話し合いをしておきましょう。
司法書士法人・行政書士鴨川事務所では、相続に関するお問い合わせを随時受け付けております。相続で不安に感じていることや悩みなど、1人で抱えこまずにぜひ私たちへご相談ください。